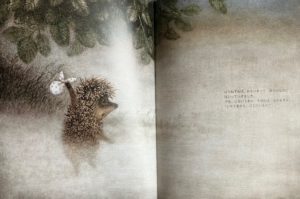ユング心理学についてのYouTubeをみていたら、「自己実現」について語られるくだりがありました。
ときどき、TVなどで識者が使っているのをみかけますが、人によって解釈はさまざまのように見受けられます。
私がこの言葉を初めて気にとめたのは、カウンセリングの専門学校で学んでいた最初のころ、講義の中でさらっと出てきました。
ん、自己実現って何?
例えば、社会的に成功を収めたアーティストは自己実現した人生、ということになるのだろうか。
うーん、わかるようなわからないような…
いまひとつスッキリしなかった私は、講義後、担当講師に質問してみた(いつも教室のすみっこでひっそりとしていた私としては、とても珍しい)
講師は私の質問に直接的な答えは示さず、アブラハムマズローの欲求5段階説を紹介してくれた。
その説とは…
人の欲求はピラミッド型の5段階の階層をなしており、一番下が①生理的欲求、②③④と上に続き、最上層が⑤の自己実現欲求となっている。
⑤自己実現欲求(自己のうちに潜在している可能性を最大限に開発し、実現して生きる)
④承認欲求(人や社会から認められたい) ↑
③所属・愛情欲求(グループに属し、愛情を求める) ↑
②安全欲求(危険のない安全な生活) ↑
①生理的欲求(食欲、睡眠欲、排泄欲) ↑
下層の欲求が満たされるごとに、段階的に上へと進み、最終的には最上層の⑤自己実現欲求を満たそうとするわけです。
ふむふむ、①~④はわかりやすい、でもやはり⑤の自己実現はわかりにくいなあ…と思った。
???な顔をしている私に講師は、「余計混乱させちゃったかな? アハハ…」とのたまい、教室を去っていきました。
今思うと、あのとき講師は、「これから長い時間をかけて、あなた自身が答えを求め、あなたの自己実現を探求するのだ」とこちらに投げかけたような気がするのです。
あれから十数年がたち、少しばかり私のなかで自己実現とはこんな感じか…くらいの輪郭はみえてきた。
自分が実現するにはまだまだ道は遠いですが…
人の評価など気にしているうちはまだ④の承認欲求のあたりをうろついているのだと思う。
ただ私の感覚では、階層の境目はもっと曖昧なものではないかと思う。
そしてどの段階にいたとしても、①~⑤すべての欲求をいくらかずつ包含しているのではないかと思う。
人は複雑なものだと思うから。
ときどき、限りなく自己実現に近い人生を歩んでいるのだろうと思わせる人を、TVなどでみかけることがあります。
例えば、農業とか漁業を生業にしてきたお爺さんの、しわ深く日に焼けたお顔のなんと魅力的なこと…
誰かに評価されようなんて意識すらない人生。
ただ自然の中で、来る日も来る日も好きな仕事をし、ほどほどに生活の糧を得て、自分が満ち足りていることがすべて。
この方たちの圧倒的な存在感の前では、自己実現なんて言葉すら形見が狭いよ……
 ねーこは こたつで 丸くなる ♪♪
ねーこは こたつで 丸くなる ♪♪
 岡山から届いた水仙 季節外れのエゴノキの花
岡山から届いた水仙 季節外れのエゴノキの花 右が地植え
右が地植え ほらほら……
ほらほら…… 品種はブルームーン 花言葉は「神の祝福」
品種はブルームーン 花言葉は「神の祝福」 ねーこは こたつで 丸くなる ♪♪
ねーこは こたつで 丸くなる ♪♪ 福山城 福山駅のホームからこの近さ
福山城 福山駅のホームからこの近さ 兄弟かな?… 同じ顔の色違い
兄弟かな?… 同じ顔の色違い 庭にオンブバッタの大量発生
庭にオンブバッタの大量発生 余香苑 (退蔵院)
余香苑 (退蔵院) プリン・ア・ラ・モード (´▽`)わーい!
プリン・ア・ラ・モード (´▽`)わーい! 建仁寺 法堂 雲龍図
建仁寺 法堂 雲龍図